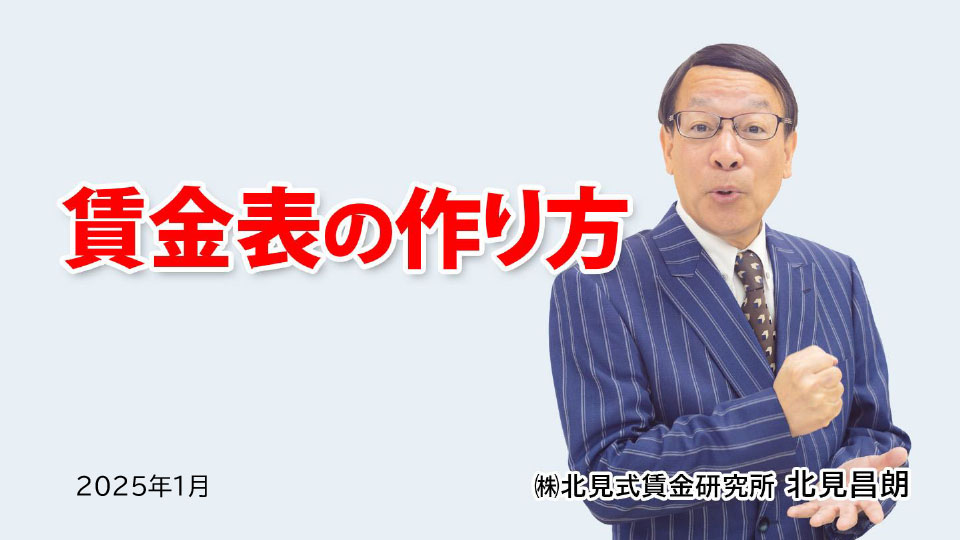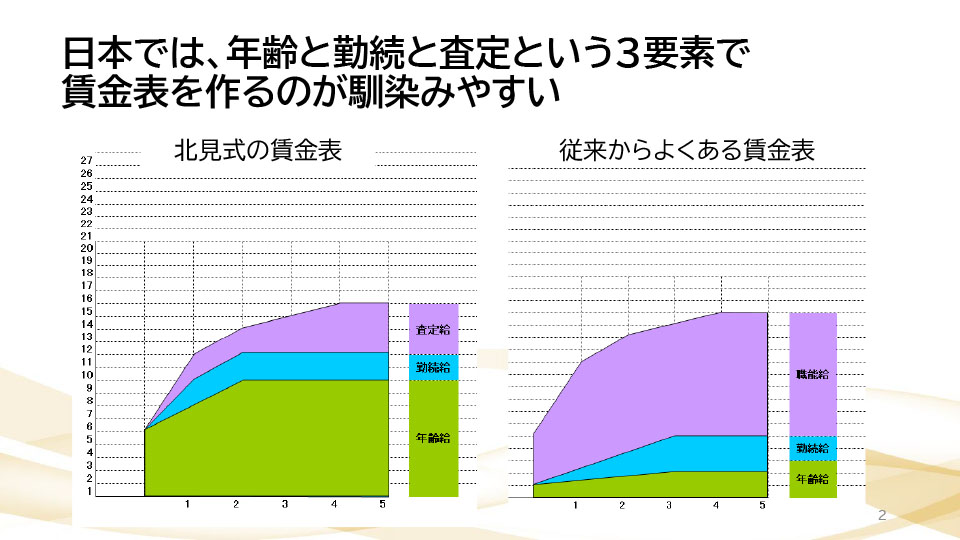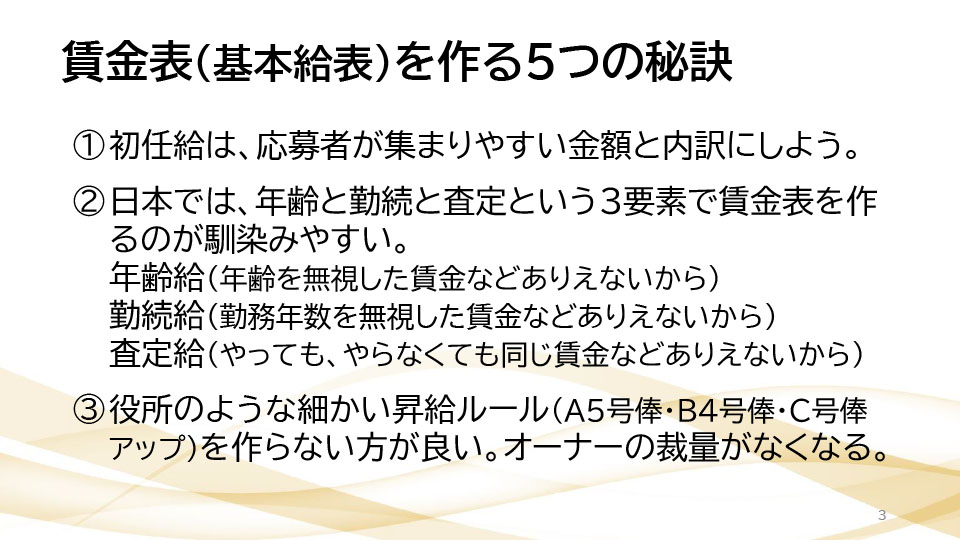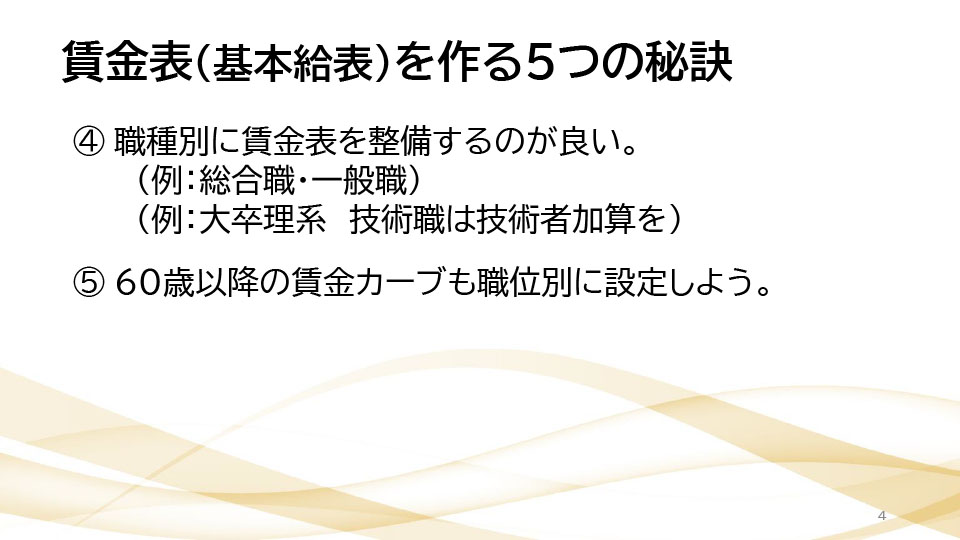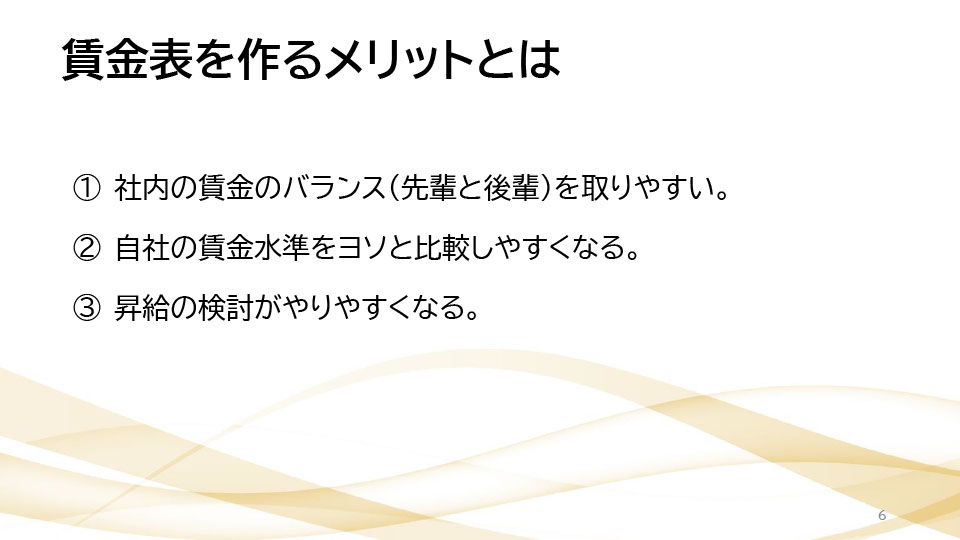賃金表の作り方
日本では、年齢と勤続と査定という3要素で
賃金表を作るのが馴染みやすい
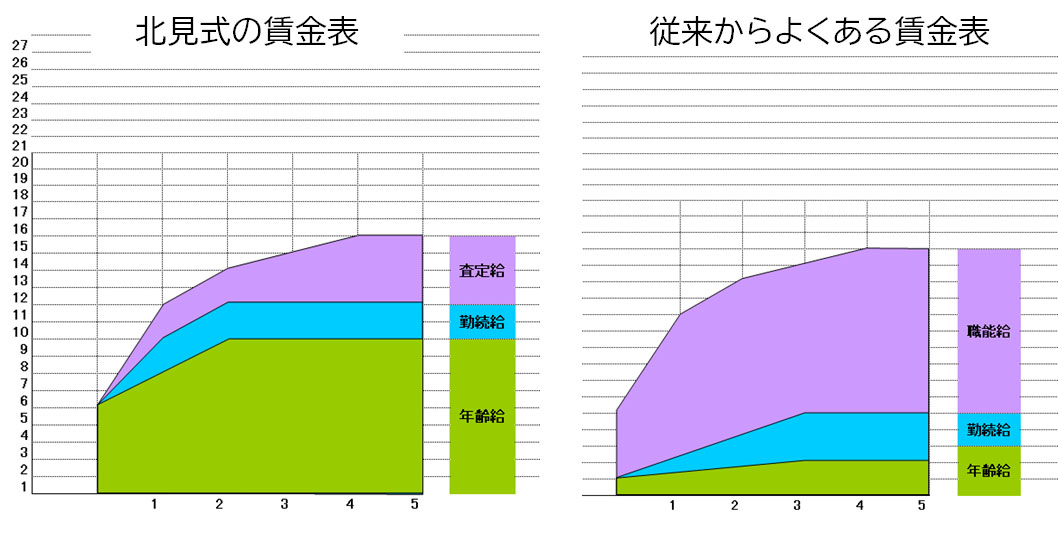
賃金表(基本給表)を作る5つの秘訣
- 初任給は、応募者が集まりやすい金額と内訳にしよう。
- 日本では、年齢と勤続と査定という3要素で賃金表を作るのが馴染みやすい。
年齢給(年齢を無視した賃金などありえないから)
勤続給(勤務年数を無視した賃金などありえないから)
査定給(やっても、やらなくても同じ賃金などありえないから) - 役所のような細かい昇給ルール(A5号俸・B4号俸・C号俸アップ)を作らない方が良い。オーナーの裁量がなくなる。
- 職種別に賃金表を整備するのが良い。
(例:総合職・一般職)
(例:大卒理系 技術職は技術者加算を) - 60歳以降の賃金カーブも職位別に設定しよう。
北見式賃金表の概要
- 年齢給(総合職の場合、35歳まで上がる)
- 勤続給(総合職の場合、10年間まで上がる)
- 査定給(35歳以降は、仕事のレベルが上がれば昇給がある)
賃金表を作るメリットとは
- 社内の賃金のバランス(先輩と後輩)を取りやすい。
- 自社の賃金水準をヨソと比較しやすくなる。
- 昇給の検討がやりやすくなる。
セミナーはこちら